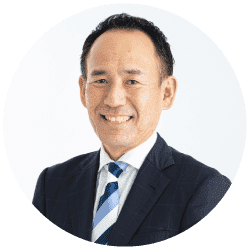建設業で特定技能外国人を受け入れる手続き方法について解説!
2025/4/14
2025/06/05
近年、建設業界では深刻な人手不足が課題となっており、外国人の雇用を検討する経営者も増えています。
日本の建設業で外国人を雇用するには、受け入れ可能な職種やビザの条件を確認し、万全な受け入れ体制を整えることが重要です。
本記事では、建設業における特定技能外国人の受け入れ手続きについて詳しく解説します。
これから特定技能外国人の雇用を検討している方や、現在雇用している技能実習生を特定技能外国人として受け入れたいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
Contents
建設業で特定技能外国人を雇用できる職種
特定技能の建設分野は以下の 3つの業務区分 に分かれており、それぞれに対応した業務区分の資格を持つ外国人のみが業務を行うことができます。
【建設分野の業務区分】
業務区分
業務内容
土木区分
コンクリート圧送・とび・建設機械施工・塗装など
建築区分
建築大工・鉄筋施工・屋根ふき・左官・内装仕上げなど
ライフライン・設備区分
配管・保温保冷・電気通信・電気工事など
在留資格上の業務区分は作業の性質をもとにして分類されていますので、作業現場の種類に問わずに勤務することができます。
例えば、土木の業務区分で特定技能を外国人が取得している場合は、建築現場であっても、土木業務を行うことができます。
特定技能外国人を雇用する際は、 自社の任せたい業務対象区分の特定技能を取得しているかを確認しましょう。
特定技能外国人を雇い入れるまでの手続き
特定技能を雇い入れるまでの手続きは、大きく7つのステップに分かれています。
+【1号特定技能外国人を受け入れるための手続き】
- 建設業法第3条許可の取得をする
- 建設技能人材機構(JAC)の会員になる
- 建設キャリアアップシステムへの登録をする
- 特定技能雇用契約の締結する
- 建設特定技能受入計画の認定申請をおこなう
- 1号特定技能外国人支援計画の作成をおこなう
- 在留資格の変更・認定の手続きを行う
新たに特定技能外国人を職場に受け入れる場合はもちろん、技能実習生として働いてた外国人を特定技能に切り替える場合も、上記の手続きを順番に進めていく必要があります。
手続きごとに必要な期間が異なるため、計画的に進めることが重要です。
それぞれの手続きの内容をしっかり押さえておきましょう。
建設業許可(建設業法第3条許可)の取得をする
特定技能外国人を雇用するためには、建設業許可(建設業法第3条許可)を取得していることが求められます。これは後の建設特定技能受入計画の認定申請で必要になるためです。
建設業許可をまだ取得していない法人は、都道府県または国土交通省に申請を行うことになります。
建設業許可の審査には、1〜2か月ほどかかるため、余裕を持って手続きを進めなければなりません。具体的な進め方を知りたいという方は、「建設業許可の申請をする時に必要な書類と記載すべき内容について解説」を参考にしてみてください。
建設技能人材機構(JAC)の会員になる
特定技能外国人を雇用するためには、受入企業は建設技能人材機構(JAC)に加入する必要があります。
「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について(平成30年12月25日閣議決定)」に基づき、JACへの加入が義務付けられているからです。
建設技能人材機構(JAC)への加入方法は2通りの方法があります。
【建設技能人材機構(JAC)への加入方法】
1,間接的に加入する方法
2,直接的に加入する方法
間接的な加入方法としては、JACの正会員である建設業団体に所属する手段があります。
直接加入をしている訳ではないのでJACの年間費用がかかることはありませんが、建設業団体が定める会費の負担は必要です。
一方で直接的に加入する場合は、年会費24万円を支払う必要があり、JACの理事会の承認も必要です。
「特定技能人材機構(JAC)入会のご案内」では、正会員である建設業団体のリストがのっておりますので、間接的な入会手続きについてはそれぞれの団体に確認をしましょう。
建設キャリアアップシステムへ登録をする
特定技能外国人を受け入れるためには、建設キャリアアップシステムへの登録が必要です。
建設キャリアアップシステムは、建設技能者の資格や現場就業履歴、社会保険の加入状況などを業界横断的に登録・蓄積する仕組みであり、特定技能外国人を受け入れる企業にとって重要な要件の一つです。
受け入れ企業は、後の手続きで必要である建設特定技能受入計画において、建設キャリアアップシステムへの登録後に交付される「事業者ID」が必要になります。
また、既に日本国内に在留している外国人を雇用する場合には、外国人の建設キャリアップ技能IDと建設キャリアアップカードの写しが必要になります。
海外から来日する外国人を雇用する場合には、雇用予定の外国人が入国後一か月以内に「技能ID」と建設キャリアップを取得する必要があります。
そのため、日本に在留している外国人にはIDとカードを準備して貰い、海外から来日する外国人を雇用する際は事前にアナウンスしておくとスムーズに手続きが進められます。
特定技能雇用契約の締結する
特定技能外国人を受け入れる企業は、雇用契約に関する重要事項を明確にした上で、
特定技能雇用契約を雇用する外国人との間で締結する必要があります。
受入企業は、必ず「雇用契約に係る重要事項事前説明書」(告示様式第2(第3条関係))を用い、1号特定技能外国人に支払われる報酬予定額や業務内容について、事前に十分に理解できる言語で説明しなければなりません。
また、特定技能雇用契約を締結する際は、以下の3点を遵守する必要があります。
- 報酬の額について
- 月給制の採用について
- 昇給について
これらの3つの確認を雇用する外国人との間でなされていない場合は契約が無効になる可能性が高くなるので、抜け漏れがないように必ず確認して下さい。
報酬の額について
1号特定技能外国人は一定の技能を有しているとみなされるため、「同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬」を支払うことが求められます。
受入企業は、報酬予定額を決定する際、以下の基準と比較し、適正な額を設定する必要があります。
- 同じ事業所内の同等技能を有する日本人技能者の賃金
- 事業所が位置する圏域内における同一又は類似職種の賃金水準
- 全国における同一又は類似職種の賃金水準
国土交通省の地方整備局による審査で、報酬額が低いと判断された場合、引き上げが求められます。その際、再度重要事項説明や契約締結の手続きを行わなければならないので注意しましょう。
月給制の採用について
特定技能外国人の報酬は、安定性を確保するために「月給制」で採用する必要があります。日給制や時給制では、工事受注状況によって収入が不安定になり、労働意欲の低下や外国人労働者の失踪リスクが高まるためです。
「月給制」とは、基本給、毎月固定的に支払われる手当及び残業代の合計額を1か月単位で支払う仕組みを指します。他の職員が日給制・時給制であっても、1号特定技能外国人には月給制を適用しなければなりません。
昇給等について
特定技能外国人の在留期間は最長5年と定められており、その期間内で技能の習熟に応じた昇給が求められます。以下の要因に基づき、昇給を行う必要があります。
- 実務経験年数の増加
- 資格・技能検定の取得
- 建設キャリアアップシステムにおける能力評価の向上
さらに、賞与、各種手当、退職金についても、日本人と同等の条件で支給する必要があり、不利な待遇は認められませんので気を付けましょう。
建設特定技能受入計画の認定申請をおこなう
特定技能外国人を雇用する際には、建設特定技能受入計画を作成し、国土交通大臣に認定申請を行うことが必ず必要です。
そのためには、建設特定技能受入計画が適切に作成され、認定基準を満たすことが求められます。
【建設特定技能受入計画の主な認定基準】
- 建設特定技能受入計画の主な認定基準
- 受入企業は建設業法第3条の許可を受けていること
- 受入企業及び1号特定技能外国人の建設キャリアアップシステムへの登録
- JACへの加入及びJACが策定した行動規範(資料7参照)の遵守
- 特定技能外国人の報酬額が同等の技能を有する日本人と同等額以上、安定的な賃金支払い(月給制)、技能習熟等に応じた昇給
- 賃金等の契約上の重要事項を書面で事前説明(外国人が十分に理解できる言語)
- 1号特定技能外国人に対し、受入れ後、国土交通大臣が指定する講習・研修を受講させること
- 国又は適正就労監理機関((一財)国際建設技能振興機構(FITS))による受入計画の適正な履行に係る巡回指導の受入れ
また、受け入れ計画の申請には、「外国人就労システム」でのオンラインでの手続きが必要になります。
申請から認定までは2か月から3か月程度の期間を要しますので、受入企業は上記の認定基準の早めの準備を心がけましょう。
1号特定技能外国人支援計画の作成をおこなう
受け入れ企業は特定技能1号の外国人が円滑に活動できるよう支援する義務があるため、
「一号特定技能外国人支援計画」は在留資格変更許可申請または在留資格認定証明書交付申請時に提出が義務付けられています。
「1号特定技能外国人支援計画」には、労働条件の確認や日本語教育、住居の提供、文化や慣習の教育など職業生活、日常生活、社会生活に関する支援が含まれます。
一号特定技能外国人支援計画の作成は、受け入れ企業側で作成するか、行政書士や法務省の登録支援機関に作成を依頼して進める必要があります。自社で作成する場合は、「出入国在留管理庁」のフォーマットを参考にしてください。
受入企業は支援計画を作成し、法令に従った支援が行われることを確認する必要がありますので、早めの準備を進めましょう。
在留資格の変更か認定の手続きを行う
日本国内に在留している外国人を採用する場合と、海外から来日する外国人を採用する場合で、それぞれ異なる申請手続きが必要です。
(1) 日本国内に在留している外国人を採用する場合(在留資格変更許可申請)
日本国内で技能実習2号を良好に修了する見込みの外国人を特定技能1号外国人として採用する場合、在留資格変更許可申請が必要です。申請時には、1号特定技能外国人支援計画も提出する必要があります。
(2) 海外から来日する外国人を採用する場合(在留資格認定証明書交付申請)
海外から技能実習2号を良好に修了した外国人を採用する場合、在留資格認定証明書交付申請が必要です。こちらも、1号特定技能外国人支援計画が必要となります。
国内の修了見込者の場合は在留満了期間の2か月前を、海外の修了見込者を採用する場合は入国予定日の3か月前を目安に準備を進めてください。
特定技能外国人を雇い入れた後の手続き
特定技能外国人を雇い入れた後の手続きも進めることが重要です。
【1号特定技能外国人を受け入れた後の手続き】
- 1号特定技能外国人受入報告書を提出する
- 受入れ後講習の受講を行う
特定技能を雇い入れた後に必要な手続きは、大きく2つのステップに分かれています。
それぞれの手続きには必要な期間が異なるため、計画的に進めることが重要になるので手続きの内容を押さえていきましょう。
1号特定技能外国人受入報告書を提出する
1号特定技能外国人を受け入れた企業は、特定技能の受け入れ後に「外国人就労システム」にて受け入れ計画を提出する必要がございます。
受入報告書の提出や受入後の講習の実施は、建設業特定技能受入計画の認定要件に該当し、これを怠ると計画が認定されないためです。また、外国人の帰国や転職、受け入れ企業の倒産倒産に伴う雇用継続の不可の場合も、速やかに報告することが求められます。
受け入れ計画は、「外国人就労システム」より入力をする形になっておりますので、「建設特定技能受入計画のオンライン申請マニュアル」等を参考にしながら適切に進めましょう。
受入れ後講習の受講を行う
1号特定技能外国人に対して、受入れ後6か月以内に「受入れ後講習」を受講させることが受入企業の義務です。
この講習は、外国人労働者が適正に就労していることを確認し、巡回指導や母国語相談ホットラインなどを通じて、二重契約や虚偽申請の防止を目的としています。
講習を受けさせない場合、不正が発覚した場合には、建設特定技能受入計画の認定取り消しなど厳正な対応が取られます。
例えば、国際建設技能振興機構(FITS)から受入れ後の日時や場所について案内が届きますので、受入企業はその案内に従い、指定された講習を受講させる必要があります。受講しない場合は、認定取消などのリスクがあります。
受入れ後講習の受講を適切に行うことで、特定技能外国人の適正就労を確保し、企業が法的要件を満たし、不正のリスクを避けることができます。
参考:木材産業で特定技能外国人を受け入れるには?雇用時のルールを解説!|ビザ申請の窓口
まとめ
特定技能外国人を雇用するには、雇用前後で対応すべき事項が多くあります。
受け入れ要件が整っていない状態で雇用すると、不法就労や労働基準法違反とみなされ、罰則を受ける可能性があります。
まずは全体の流れを把握し、ひとつひとつ丁寧に手続きを進めましょう。
2025/4/14
2025/06/05
近年、建設業界では深刻な人手不足が課題となっており、外国人の雇用を検討する経営者も増えています。
日本の建設業で外国人を雇用するには、受け入れ可能な職種やビザの条件を確認し、万全な受け入れ体制を整えることが重要です。
本記事では、建設業における特定技能外国人の受け入れ手続きについて詳しく解説します。
これから特定技能外国人の雇用を検討している方や、現在雇用している技能実習生を特定技能外国人として受け入れたいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
Contents
建設業で特定技能外国人を雇用できる職種
特定技能の建設分野は以下の 3つの業務区分 に分かれており、それぞれに対応した業務区分の資格を持つ外国人のみが業務を行うことができます。
【建設分野の業務区分】
| 業務区分 | 業務内容 |
| 土木区分 | コンクリート圧送・とび・建設機械施工・塗装など |
| 建築区分 | 建築大工・鉄筋施工・屋根ふき・左官・内装仕上げなど |
| ライフライン・設備区分 | 配管・保温保冷・電気通信・電気工事など |
在留資格上の業務区分は作業の性質をもとにして分類されていますので、作業現場の種類に問わずに勤務することができます。
例えば、土木の業務区分で特定技能を外国人が取得している場合は、建築現場であっても、土木業務を行うことができます。
特定技能外国人を雇用する際は、 自社の任せたい業務対象区分の特定技能を取得しているかを確認しましょう。
特定技能外国人を雇い入れるまでの手続き
特定技能を雇い入れるまでの手続きは、大きく7つのステップに分かれています。
+【1号特定技能外国人を受け入れるための手続き】
- 建設業法第3条許可の取得をする
- 建設技能人材機構(JAC)の会員になる
- 建設キャリアアップシステムへの登録をする
- 特定技能雇用契約の締結する
- 建設特定技能受入計画の認定申請をおこなう
- 1号特定技能外国人支援計画の作成をおこなう
- 在留資格の変更・認定の手続きを行う
新たに特定技能外国人を職場に受け入れる場合はもちろん、技能実習生として働いてた外国人を特定技能に切り替える場合も、上記の手続きを順番に進めていく必要があります。
手続きごとに必要な期間が異なるため、計画的に進めることが重要です。
それぞれの手続きの内容をしっかり押さえておきましょう。
建設業許可(建設業法第3条許可)の取得をする
特定技能外国人を雇用するためには、建設業許可(建設業法第3条許可)を取得していることが求められます。これは後の建設特定技能受入計画の認定申請で必要になるためです。
建設業許可をまだ取得していない法人は、都道府県または国土交通省に申請を行うことになります。
建設業許可の審査には、1〜2か月ほどかかるため、余裕を持って手続きを進めなければなりません。具体的な進め方を知りたいという方は、「建設業許可の申請をする時に必要な書類と記載すべき内容について解説」を参考にしてみてください。
建設技能人材機構(JAC)の会員になる
特定技能外国人を雇用するためには、受入企業は建設技能人材機構(JAC)に加入する必要があります。
「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について(平成30年12月25日閣議決定)」に基づき、JACへの加入が義務付けられているからです。
建設技能人材機構(JAC)への加入方法は2通りの方法があります。
【建設技能人材機構(JAC)への加入方法】
1,間接的に加入する方法
2,直接的に加入する方法
間接的な加入方法としては、JACの正会員である建設業団体に所属する手段があります。
直接加入をしている訳ではないのでJACの年間費用がかかることはありませんが、建設業団体が定める会費の負担は必要です。
一方で直接的に加入する場合は、年会費24万円を支払う必要があり、JACの理事会の承認も必要です。
「特定技能人材機構(JAC)入会のご案内」では、正会員である建設業団体のリストがのっておりますので、間接的な入会手続きについてはそれぞれの団体に確認をしましょう。
建設キャリアアップシステムへ登録をする
特定技能外国人を受け入れるためには、建設キャリアアップシステムへの登録が必要です。
建設キャリアアップシステムは、建設技能者の資格や現場就業履歴、社会保険の加入状況などを業界横断的に登録・蓄積する仕組みであり、特定技能外国人を受け入れる企業にとって重要な要件の一つです。
受け入れ企業は、後の手続きで必要である建設特定技能受入計画において、建設キャリアアップシステムへの登録後に交付される「事業者ID」が必要になります。
また、既に日本国内に在留している外国人を雇用する場合には、外国人の建設キャリアップ技能IDと建設キャリアアップカードの写しが必要になります。
海外から来日する外国人を雇用する場合には、雇用予定の外国人が入国後一か月以内に「技能ID」と建設キャリアップを取得する必要があります。
そのため、日本に在留している外国人にはIDとカードを準備して貰い、海外から来日する外国人を雇用する際は事前にアナウンスしておくとスムーズに手続きが進められます。
特定技能雇用契約の締結する
特定技能外国人を受け入れる企業は、雇用契約に関する重要事項を明確にした上で、
特定技能雇用契約を雇用する外国人との間で締結する必要があります。
受入企業は、必ず「雇用契約に係る重要事項事前説明書」(告示様式第2(第3条関係))を用い、1号特定技能外国人に支払われる報酬予定額や業務内容について、事前に十分に理解できる言語で説明しなければなりません。
また、特定技能雇用契約を締結する際は、以下の3点を遵守する必要があります。
- 報酬の額について
- 月給制の採用について
- 昇給について
これらの3つの確認を雇用する外国人との間でなされていない場合は契約が無効になる可能性が高くなるので、抜け漏れがないように必ず確認して下さい。
報酬の額について
1号特定技能外国人は一定の技能を有しているとみなされるため、「同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬」を支払うことが求められます。
受入企業は、報酬予定額を決定する際、以下の基準と比較し、適正な額を設定する必要があります。
- 同じ事業所内の同等技能を有する日本人技能者の賃金
- 事業所が位置する圏域内における同一又は類似職種の賃金水準
- 全国における同一又は類似職種の賃金水準
国土交通省の地方整備局による審査で、報酬額が低いと判断された場合、引き上げが求められます。その際、再度重要事項説明や契約締結の手続きを行わなければならないので注意しましょう。
月給制の採用について
特定技能外国人の報酬は、安定性を確保するために「月給制」で採用する必要があります。日給制や時給制では、工事受注状況によって収入が不安定になり、労働意欲の低下や外国人労働者の失踪リスクが高まるためです。
「月給制」とは、基本給、毎月固定的に支払われる手当及び残業代の合計額を1か月単位で支払う仕組みを指します。他の職員が日給制・時給制であっても、1号特定技能外国人には月給制を適用しなければなりません。
昇給等について
特定技能外国人の在留期間は最長5年と定められており、その期間内で技能の習熟に応じた昇給が求められます。以下の要因に基づき、昇給を行う必要があります。
- 実務経験年数の増加
- 資格・技能検定の取得
- 建設キャリアアップシステムにおける能力評価の向上
さらに、賞与、各種手当、退職金についても、日本人と同等の条件で支給する必要があり、不利な待遇は認められませんので気を付けましょう。
建設特定技能受入計画の認定申請をおこなう
特定技能外国人を雇用する際には、建設特定技能受入計画を作成し、国土交通大臣に認定申請を行うことが必ず必要です。
そのためには、建設特定技能受入計画が適切に作成され、認定基準を満たすことが求められます。
【建設特定技能受入計画の主な認定基準】
- 建設特定技能受入計画の主な認定基準
- 受入企業は建設業法第3条の許可を受けていること
- 受入企業及び1号特定技能外国人の建設キャリアアップシステムへの登録
- JACへの加入及びJACが策定した行動規範(資料7参照)の遵守
- 特定技能外国人の報酬額が同等の技能を有する日本人と同等額以上、安定的な賃金支払い(月給制)、技能習熟等に応じた昇給
- 賃金等の契約上の重要事項を書面で事前説明(外国人が十分に理解できる言語)
- 1号特定技能外国人に対し、受入れ後、国土交通大臣が指定する講習・研修を受講させること
- 国又は適正就労監理機関((一財)国際建設技能振興機構(FITS))による受入計画の適正な履行に係る巡回指導の受入れ
また、受け入れ計画の申請には、「外国人就労システム」でのオンラインでの手続きが必要になります。
申請から認定までは2か月から3か月程度の期間を要しますので、受入企業は上記の認定基準の早めの準備を心がけましょう。
1号特定技能外国人支援計画の作成をおこなう
受け入れ企業は特定技能1号の外国人が円滑に活動できるよう支援する義務があるため、
「一号特定技能外国人支援計画」は在留資格変更許可申請または在留資格認定証明書交付申請時に提出が義務付けられています。
「1号特定技能外国人支援計画」には、労働条件の確認や日本語教育、住居の提供、文化や慣習の教育など職業生活、日常生活、社会生活に関する支援が含まれます。
一号特定技能外国人支援計画の作成は、受け入れ企業側で作成するか、行政書士や法務省の登録支援機関に作成を依頼して進める必要があります。自社で作成する場合は、「出入国在留管理庁」のフォーマットを参考にしてください。
受入企業は支援計画を作成し、法令に従った支援が行われることを確認する必要がありますので、早めの準備を進めましょう。
在留資格の変更か認定の手続きを行う
日本国内に在留している外国人を採用する場合と、海外から来日する外国人を採用する場合で、それぞれ異なる申請手続きが必要です。
(1) 日本国内に在留している外国人を採用する場合(在留資格変更許可申請)
日本国内で技能実習2号を良好に修了する見込みの外国人を特定技能1号外国人として採用する場合、在留資格変更許可申請が必要です。申請時には、1号特定技能外国人支援計画も提出する必要があります。
(2) 海外から来日する外国人を採用する場合(在留資格認定証明書交付申請)
海外から技能実習2号を良好に修了した外国人を採用する場合、在留資格認定証明書交付申請が必要です。こちらも、1号特定技能外国人支援計画が必要となります。
国内の修了見込者の場合は在留満了期間の2か月前を、海外の修了見込者を採用する場合は入国予定日の3か月前を目安に準備を進めてください。
特定技能外国人を雇い入れた後の手続き
特定技能外国人を雇い入れた後の手続きも進めることが重要です。
【1号特定技能外国人を受け入れた後の手続き】
- 1号特定技能外国人受入報告書を提出する
- 受入れ後講習の受講を行う
特定技能を雇い入れた後に必要な手続きは、大きく2つのステップに分かれています。
それぞれの手続きには必要な期間が異なるため、計画的に進めることが重要になるので手続きの内容を押さえていきましょう。
1号特定技能外国人受入報告書を提出する
1号特定技能外国人を受け入れた企業は、特定技能の受け入れ後に「外国人就労システム」にて受け入れ計画を提出する必要がございます。
受入報告書の提出や受入後の講習の実施は、建設業特定技能受入計画の認定要件に該当し、これを怠ると計画が認定されないためです。また、外国人の帰国や転職、受け入れ企業の倒産倒産に伴う雇用継続の不可の場合も、速やかに報告することが求められます。
受け入れ計画は、「外国人就労システム」より入力をする形になっておりますので、「建設特定技能受入計画のオンライン申請マニュアル」等を参考にしながら適切に進めましょう。
受入れ後講習の受講を行う
1号特定技能外国人に対して、受入れ後6か月以内に「受入れ後講習」を受講させることが受入企業の義務です。
この講習は、外国人労働者が適正に就労していることを確認し、巡回指導や母国語相談ホットラインなどを通じて、二重契約や虚偽申請の防止を目的としています。
講習を受けさせない場合、不正が発覚した場合には、建設特定技能受入計画の認定取り消しなど厳正な対応が取られます。
例えば、国際建設技能振興機構(FITS)から受入れ後の日時や場所について案内が届きますので、受入企業はその案内に従い、指定された講習を受講させる必要があります。受講しない場合は、認定取消などのリスクがあります。
受入れ後講習の受講を適切に行うことで、特定技能外国人の適正就労を確保し、企業が法的要件を満たし、不正のリスクを避けることができます。
参考:木材産業で特定技能外国人を受け入れるには?雇用時のルールを解説!|ビザ申請の窓口
まとめ
特定技能外国人を雇用するには、雇用前後で対応すべき事項が多くあります。
受け入れ要件が整っていない状態で雇用すると、不法就労や労働基準法違反とみなされ、罰則を受ける可能性があります。
まずは全体の流れを把握し、ひとつひとつ丁寧に手続きを進めましょう。