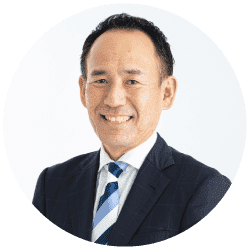初めて外国人を雇用した在留資格の確認から手続きと注意点まで解説
2025/7/15
2025/07/18
初めて外国人を雇用する際、まず確認すべきは「在留資格」です。
在留資格とは、外国人が日本に滞在し、活動するために必要な資格であり、種類によって日本で認められる活動範囲が異なります。適切な在留資格を持たない外国人を雇用すると、企業側も不法就労助長罪に問われる可能性があります。
外国人の雇用を検討する企業は、在留資格制度を正しく理解し、適切な手続きを行う必要があります。
この記事では、外国人雇用における在留資格の基礎知識から、必要な手続き、よくある失敗とその対策までを詳しく解説します。
Contents
外国人が日本で働くために必要な在留資格の種類
外国人が日本で合法的に働くためには、就労可能な在留資格を持っているかどうかの確認が不可欠です。在留資格には、大きく分けて以下の2種類があります。
1-1. 就労制限のない在留資格(身分・地位に基づく在留資格)
在留資格を持つ外国人は、活動内容に制限がなく、日本でどのような仕事でも自由に就労できます。
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
1-2. 就労制限のある在留資格(活動資格)
特定の活動のみが許可される在留資格で、雇用する外国人がどのような活動資格を持っているかによって、日本で行える仕事の種類や期間が定められます。
活動資格を持つ外国人を雇用する場合、その在留資格で認められている範囲内の業務に従事させなければなりません。異なる業務に従事させた場合、不法就労とみなされ、企業が罰則の対象となる可能性があります。
主な活動資格と従事できる仕事の例は以下の通りです。
在留資格名
従事できる仕事の例
特徴・補足
技術・人文知識・国際業務
通訳、翻訳、デザイナー、ITエンジニア、経理、営業、マーケティングなど
専門的な知識や技術を要するホワイトカラー業務が対象です。大学や専門学校で専門分野を修了していること、または一定の実務経験が求められます。
技能
料理人、建設作業員、パイロット、スポーツ指導者など
特定の熟練した技能を必要とする業務が対象です。長年の実務経験や技能に関する資格が求められることが多く、就労できる分野が限定されます。
特定技能
農業、漁業、介護、建設、飲食料品製造、外食など
特定産業分野における人手不足に対応するため創設されました。特定技能1号は相当程度の知識または経験、特定技能2号は熟練した技能を要します。技能実習を修了した外国人が移行することも多いです。
特定活動
ワーキングホリデー、インターンシップ、研究活動など
個別の活動内容に応じて法務大臣が指定する在留資格です。活動内容は個々に異なるため、必ず許可された活動範囲を確認する必要があります。
留学
(原則就労不可)
学業を目的とする在留資格のため、原則として就労はできません。ただし、「資格外活動許可」を取得すれば、週28時間以内(長期休暇中は1日8時間以内)のアルバイトが可能です。
家族滞在
(原則就労不可)
在留外国人が扶養する配偶者や子の在留資格のため、原則として就労はできません。ただし、「資格外活動許可」を取得すれば、週28時間以内のアルバイトが可能です。
2. 外国人を雇用する企業が必ず行うべき手続き
外国人を適法に雇用し、企業が不法就労助長罪に問われることを防ぐためには、以下の手続きを漏れなく行う必要があります。
手続き名
目的と概要
在留カードの確認
目的: 外国人の身分証明、在留資格、在留期間、就労制限の有無などを確認するため。偽造防止措置が施されており、不法滞在者や不法就労者を雇用するリスクを減らします。
確認事項: 氏名、生年月日、国籍・地域、在留資格、在留期間、就労制限の有無、住居地、交付年月日、有効期間など。特に裏面の「就労制限の有無」は必ず確認しましょう。
資格外活動許可の確認
目的: 「留学」や「家族滞在」など、原則として就労が認められていない在留資格の外国人が、アルバイトなどの活動を行うために必要です。この許可がないのに就労させた場合、企業も処罰の対象となります。
確認事項: 在留カードの裏面に「許可」の記載があるか、または別途交付された「資格外活動許可書」の提示を求めます。
就労資格証明書の確認
目的: 外国人が持つ在留資格でどのような仕事ができるか、法務大臣が証明するものです。外国人本人だけでなく、雇用する企業側も、雇用しようとする業務が適法な就労活動であることを事前に確認できるため、不法就労のリスクを軽減できます。
取得方法: 外国人本人または代理人が、出入国在留管理庁に申請することで交付されます。
雇用対策法に基づく届出
目的: ハローワークに対し、外国人の雇用状況に関する情報(氏名、在留資格、在留期間など)を届け出ることで、外国人の雇用管理の適正化を図ります。
注意点: 雇用保険の適用事業所の事業主は、外国人労働者の雇用時と離職時にハローワークへ届け出ることが義務付けられています。怠った場合、指導の対象となる可能性があります。
社会保険・労働保険の手続き
目的: 日本国内で働く外国人労働者も、日本人と同様に社会保険(健康保険、厚生年金)や労働保険(雇用保険、労災保険)の適用対象となります。
注意点: これらへの加入は企業の義務であり、手続きを怠ると罰則や追徴金が発生する可能性があります。各保険制度の加入要件を確認し、適切に手続きを行いましょう。
企業担当者が今すぐ確認すべきこと
- 採用を検討している外国人の在留カード(特に裏面)を必ず確認する必要があります。
- 就労制限のある在留資格の場合は、雇用しようとする業務がその資格の範囲内であるかを慎重に確認をして、必要に応じて就労資格証明書の提示を求めましょう。
外国人雇用でよくある失敗事例と効果的な対策
外国人雇用において、企業が予期せぬトラブルに巻き込まれるケースは少なくありません。ここでは、よくある失敗とその対策について解説します。
3-1. 在留資格と業務内容の不一致によるリスク
最もよくある失敗の一つに、在留資格で認められている活動範囲を超えた業務に従事させてしまうケースがあります。例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人に、単純労働をさせてしまうなどが該当します。
これは不法就労とみなされ、企業が不法就労助長罪(3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方)の対象となる可能性があります。
対策:採用前に外国人の在留資格を詳細に確認し、雇用しようとする業務内容がその在留資格で許可されている活動範囲内であることを明確にすることが重要です。採用面接時や内定時に、具体的な業務内容を十分に説明し、双方の認識を一致させましょう。
3-2. 在留期間の管理不足
在留期間の管理を怠り、期間満了前に更新手続きが行われず、外国人が不法滞在となってしまうケースも散見されます。不法滞在者を雇用し続けることは、企業が不法就労助長罪に問われる直接的な原因となります。
対策:外国人従業員の在留期間を定期的に確認し、期間満了の数ヶ月前には本人に更新手続きを促す、または手続きのサポートを行う体制を整えましょう。社内で在留期間管理表を作成し、アラート機能などを活用することも有効です。
3-3. 雇用後のフォローアップ不足
外国人従業員は、日本の文化や労働習慣に不慣れな場合があります。十分なオリエンテーションや業務指示がないと、誤解が生じやすく、業務効率の低下やトラブルの原因となることがあります。
対策:入社時のオリエンテーションを丁寧に行い、就業規則や職場のルール、福利厚生などを多言語で説明するなどの工夫が必要です。また、定期的な面談を通じて、業務上の課題や生活面の相談に対応することで、外国人従業員が安心して働ける環境を整備しましょう。
まとめ
初めて外国人を雇用する企業にとって、在留資格の理解と適切な手続きは必須です。外国人が日本で働くためには、就労可能な在留資格の確認が不可欠であり、その資格によって従事できる業務が決まります。
企業は、在留カードの確認や雇用対策法に基づく届出、社会保険・労働保険の手続きなど、必要な手続きを漏れなく行う必要があります。また、在留資格と業務内容の不一致や在留期間の管理不足といった失敗を避け、外国人を適法に雇用するためにも、専門家である行政書士に相談することを強く推奨します。
外国人雇用に関してご不明な点があれば、複雑な手続きや法的リスクを回避するためにも、ぜひお気軽にご相談ください。
2025/7/15
2025/07/18
初めて外国人を雇用する際、まず確認すべきは「在留資格」です。
在留資格とは、外国人が日本に滞在し、活動するために必要な資格であり、種類によって日本で認められる活動範囲が異なります。適切な在留資格を持たない外国人を雇用すると、企業側も不法就労助長罪に問われる可能性があります。
外国人の雇用を検討する企業は、在留資格制度を正しく理解し、適切な手続きを行う必要があります。
この記事では、外国人雇用における在留資格の基礎知識から、必要な手続き、よくある失敗とその対策までを詳しく解説します。
Contents
外国人が日本で働くために必要な在留資格の種類
外国人が日本で合法的に働くためには、就労可能な在留資格を持っているかどうかの確認が不可欠です。在留資格には、大きく分けて以下の2種類があります。
1-1. 就労制限のない在留資格(身分・地位に基づく在留資格)
在留資格を持つ外国人は、活動内容に制限がなく、日本でどのような仕事でも自由に就労できます。
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
1-2. 就労制限のある在留資格(活動資格)
特定の活動のみが許可される在留資格で、雇用する外国人がどのような活動資格を持っているかによって、日本で行える仕事の種類や期間が定められます。
活動資格を持つ外国人を雇用する場合、その在留資格で認められている範囲内の業務に従事させなければなりません。異なる業務に従事させた場合、不法就労とみなされ、企業が罰則の対象となる可能性があります。
主な活動資格と従事できる仕事の例は以下の通りです。
| 在留資格名 | 従事できる仕事の例 | 特徴・補足 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 通訳、翻訳、デザイナー、ITエンジニア、経理、営業、マーケティングなど | 専門的な知識や技術を要するホワイトカラー業務が対象です。大学や専門学校で専門分野を修了していること、または一定の実務経験が求められます。 |
| 技能 | 料理人、建設作業員、パイロット、スポーツ指導者など | 特定の熟練した技能を必要とする業務が対象です。長年の実務経験や技能に関する資格が求められることが多く、就労できる分野が限定されます。 |
| 特定技能 | 農業、漁業、介護、建設、飲食料品製造、外食など | 特定産業分野における人手不足に対応するため創設されました。特定技能1号は相当程度の知識または経験、特定技能2号は熟練した技能を要します。技能実習を修了した外国人が移行することも多いです。 |
| 特定活動 | ワーキングホリデー、インターンシップ、研究活動など | 個別の活動内容に応じて法務大臣が指定する在留資格です。活動内容は個々に異なるため、必ず許可された活動範囲を確認する必要があります。 |
| 留学 | (原則就労不可) | 学業を目的とする在留資格のため、原則として就労はできません。ただし、「資格外活動許可」を取得すれば、週28時間以内(長期休暇中は1日8時間以内)のアルバイトが可能です。 |
| 家族滞在 | (原則就労不可) | 在留外国人が扶養する配偶者や子の在留資格のため、原則として就労はできません。ただし、「資格外活動許可」を取得すれば、週28時間以内のアルバイトが可能です。 |
2. 外国人を雇用する企業が必ず行うべき手続き
外国人を適法に雇用し、企業が不法就労助長罪に問われることを防ぐためには、以下の手続きを漏れなく行う必要があります。
| 手続き名 | 目的と概要 |
| 在留カードの確認 | 目的: 外国人の身分証明、在留資格、在留期間、就労制限の有無などを確認するため。偽造防止措置が施されており、不法滞在者や不法就労者を雇用するリスクを減らします。 確認事項: 氏名、生年月日、国籍・地域、在留資格、在留期間、就労制限の有無、住居地、交付年月日、有効期間など。特に裏面の「就労制限の有無」は必ず確認しましょう。 |
| 資格外活動許可の確認 | 目的: 「留学」や「家族滞在」など、原則として就労が認められていない在留資格の外国人が、アルバイトなどの活動を行うために必要です。この許可がないのに就労させた場合、企業も処罰の対象となります。 確認事項: 在留カードの裏面に「許可」の記載があるか、または別途交付された「資格外活動許可書」の提示を求めます。 |
| 就労資格証明書の確認 | 目的: 外国人が持つ在留資格でどのような仕事ができるか、法務大臣が証明するものです。外国人本人だけでなく、雇用する企業側も、雇用しようとする業務が適法な就労活動であることを事前に確認できるため、不法就労のリスクを軽減できます。 取得方法: 外国人本人または代理人が、出入国在留管理庁に申請することで交付されます。 |
| 雇用対策法に基づく届出 | 目的: ハローワークに対し、外国人の雇用状況に関する情報(氏名、在留資格、在留期間など)を届け出ることで、外国人の雇用管理の適正化を図ります。 注意点: 雇用保険の適用事業所の事業主は、外国人労働者の雇用時と離職時にハローワークへ届け出ることが義務付けられています。怠った場合、指導の対象となる可能性があります。 |
| 社会保険・労働保険の手続き | 目的: 日本国内で働く外国人労働者も、日本人と同様に社会保険(健康保険、厚生年金)や労働保険(雇用保険、労災保険)の適用対象となります。 注意点: これらへの加入は企業の義務であり、手続きを怠ると罰則や追徴金が発生する可能性があります。各保険制度の加入要件を確認し、適切に手続きを行いましょう。 |
企業担当者が今すぐ確認すべきこと
- 採用を検討している外国人の在留カード(特に裏面)を必ず確認する必要があります。
- 就労制限のある在留資格の場合は、雇用しようとする業務がその資格の範囲内であるかを慎重に確認をして、必要に応じて就労資格証明書の提示を求めましょう。
外国人雇用でよくある失敗事例と効果的な対策
外国人雇用において、企業が予期せぬトラブルに巻き込まれるケースは少なくありません。ここでは、よくある失敗とその対策について解説します。
3-1. 在留資格と業務内容の不一致によるリスク
最もよくある失敗の一つに、在留資格で認められている活動範囲を超えた業務に従事させてしまうケースがあります。例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人に、単純労働をさせてしまうなどが該当します。
これは不法就労とみなされ、企業が不法就労助長罪(3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方)の対象となる可能性があります。
対策:採用前に外国人の在留資格を詳細に確認し、雇用しようとする業務内容がその在留資格で許可されている活動範囲内であることを明確にすることが重要です。採用面接時や内定時に、具体的な業務内容を十分に説明し、双方の認識を一致させましょう。
3-2. 在留期間の管理不足
在留期間の管理を怠り、期間満了前に更新手続きが行われず、外国人が不法滞在となってしまうケースも散見されます。不法滞在者を雇用し続けることは、企業が不法就労助長罪に問われる直接的な原因となります。
対策:外国人従業員の在留期間を定期的に確認し、期間満了の数ヶ月前には本人に更新手続きを促す、または手続きのサポートを行う体制を整えましょう。社内で在留期間管理表を作成し、アラート機能などを活用することも有効です。
3-3. 雇用後のフォローアップ不足
外国人従業員は、日本の文化や労働習慣に不慣れな場合があります。十分なオリエンテーションや業務指示がないと、誤解が生じやすく、業務効率の低下やトラブルの原因となることがあります。
対策:入社時のオリエンテーションを丁寧に行い、就業規則や職場のルール、福利厚生などを多言語で説明するなどの工夫が必要です。また、定期的な面談を通じて、業務上の課題や生活面の相談に対応することで、外国人従業員が安心して働ける環境を整備しましょう。
まとめ
初めて外国人を雇用する企業にとって、在留資格の理解と適切な手続きは必須です。外国人が日本で働くためには、就労可能な在留資格の確認が不可欠であり、その資格によって従事できる業務が決まります。
企業は、在留カードの確認や雇用対策法に基づく届出、社会保険・労働保険の手続きなど、必要な手続きを漏れなく行う必要があります。また、在留資格と業務内容の不一致や在留期間の管理不足といった失敗を避け、外国人を適法に雇用するためにも、専門家である行政書士に相談することを強く推奨します。
外国人雇用に関してご不明な点があれば、複雑な手続きや法的リスクを回避するためにも、ぜひお気軽にご相談ください。